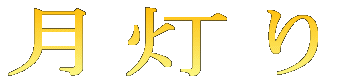
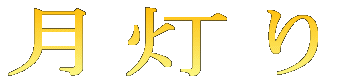
「ねぇ。起きて、起きてよ……」
「んっ……」
誰かに体を揺さぶられ、私は意識を取り戻した。どれほど気を失っていたのかはわからないが、酒
で火照っていた体がひんやりと冷えている。かなり長い時間、気を失っていたのだろう。
「あぁ、良かった。僕は人間に治癒術を施したことがなかったから、加減がわからなくてね。死ん
じゃったかと思ったよ」
ゆっくりと半身を起こす私を見ながら、魔王は肩で息をしていた。とてつもなく高度な治癒術を用
いたのだろう、額には汗も浮かんでいる。
「君は人間で、僕の敵だけど。こんな形で殺したら、フェアじゃないでしょう?」
草の上から起き上がった私は、魔王の口からこぼれ落ちた“フェア”という言葉がおかしくて吹き
出してしまう。
「魔王には、フェアや反則なんて言葉はないと思っていたけど。違ったんだな」
笑いをこらえながら私が身体についた草を払っていると、魔王はすっかり天球の中心に昇った月を
見上げた。体を射抜くような強い月光が、魔王の顔に容赦なく降り注ぐ。
「君に対しては、フェアでいたいと思っただけさ」
そう言うと、魔王は黒いローブを脱いだ。その中に隠されていた、黒い布の服を纏った脂肪も筋肉
もない薄い身体は、病的なほどに青白かった。
「僕は、自分の罪を履き違えていた。愛したことは罪なんかじゃない。それに気付かせてくれた君
にだけには、フェアでいたいんだ」
薄い身体を自分の腕で抱きしめ、魔王は不機嫌そうに闇色の目を伏せた。その表情の奥にある微か
な照れに気付いた私は、小さく息を吐く。魔王と呼ばれる存在であっても、その本質はなんら人と代
わりがないということに気付いて。
「その代わりと言ったらなんだけど、一つだけ僕のお願いを聞いてくれないかな?」
しばらく続いた沈黙の後。魔王はくるりと私の方に向き直ると、真剣なまなざしを私に向けてそう
言った。
「もし僕が君たちに敗れてしまったら。この身体が爆発して、魂が居場所をなくしたら。僕の骨を
地面深くに埋めてくれないかな」
魔王の言葉が闇の中に消えた瞬間、どうっと風が草原を吹きぬけた。その風に混ざった甘い腐臭が
、酷く物悲しい。
「わかった、約束するよ。でも。もし、あたしがあんたに負けたら。この身体が爆発して、魂が居
場所をなくしたら。あたしの身体を、さっきの炎で焼いて真っ白な灰にして欲しい」
私も真剣なまなざしで魔王を見つめ返し、ぴんと背筋を伸ばした。負けることなんかないという確
信はあるけれど、もしカナーレが危機に直面したら。きっと私は、カナーレを救うためにこの命を投
げ出すだろう。その時、死んだ私を見てカナーレが罪の意識を感じないように。跡形もなく、真っ白
い灰になりたい。私の死に際の望みはそれだけだ。
「…わかったよ。その時は君の望みを叶えてあげる」
魔王は少しだけ迷うようなそぶりを見せた後、厳粛な面持ちで頷く。私はその言葉に少しだけ安堵
し、肩の力を抜いた。
「今度君と会うときは、僕はこの姿じゃないかもしれない」
さっき脱いだばかりのローブから、小さな光る石を取り出して魔王は哀しそうに笑う。その石は何
か禍々しいものだということが、魔王の指先の震えから私にも読み取れた。
「きっと、僕はこの魔石の力で最強の怪物になっているよ。もしかしたら今日の記憶も残っていな
いかもしれない」
石を月灯りに翳しながら、魔王はかすかに眉根を寄せた。
「そのままでも、あんたは強い。こんな石っころの力なんか、借りなくてもいいじゃないか」
最強の怪物になれるという魔石を魔王の手から掠め取り、私はそう言ってふんと鼻を鳴らした。ど
れだけこの石が貴重なものであったとしても、魔族三万七百四十九種の頂点に君臨する誇り高き魔王
には無用の物だろうと思ってしまう。
「君たち人間は成長するけれど、僕にはもう成長の余地はない。成長した君たちに勝つには、この
力が必要なんだ」
魔王は豆やひび割れだらけの私の手をとり、何度も撫でさすりながら穏やかに微笑んだ。
「君の手は、成長してきた手だ。こんなにすばらしい手はないよ」
そう言うと魔王は私の手を離し、黒いローブで身体を覆った。覆ったのは身体だけなのに、さっき
まで見えていた心さえも、黒い布の向こうに隠れてしまったような気がする。
「この月灯りの中で君と話しができて、本当に良かった」
そう呟くと、魔王はすうっと闇の中に溶けて姿を消してしまった。さよならを言う暇もない、あっ
という間の幕切れ。
「あたしも、あんたと話せて良かったよ」
ただっ広い草原の中で、私と魔王は同じ月を見上げた。どちらも、報われることのない愛に傷つい
ていた。もし、二人が同じ種族に生まれていたら。そこにはきっと、紛れもない友情が育っていただ
ろう。
「愛したことは罪じゃないけど、愛されてみたかったね……」
夜明けまではまだ遠く、ただ大地に降り注ぐ月灯りだけがその闇を切り裂いていた。