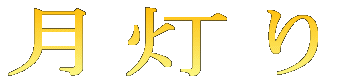
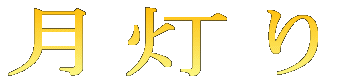
「綺麗なもんだな……」
焚き火をしていた巨木の根元から、どれくらい歩いたのか。草原の最果てにある崖にたどり尽いた
私は、空瓶をぶら下げたまま月を見上げてそう呟いた。夜空の星さえ覆い隠す強い光が、地上に降り
注ぎ、崖下の海に浮かんで揺れている。
「ここからの眺めは、なかなかのものでしょう?」
誰もいないはずの後ろから、おっとりとした男の声がして私は反射的に後ろを振り返った。
「ここはね、僕も良く来るんだよ。正義を気取った人間たちとの、戦いの疲れを癒すためにね」
シルクのローブを着た男は、にたりと皮肉めいた笑みを浮かべて私の隣に並んだ。
闇色の目に、銀色の髪。ローブの袖から見え隠れする爪は異様に長く、黒ずんでいる。そして全身
から香る、腐りかけの果物にも似た甘い香りに、私は覚えがあった。
「魔王デザンディア!」
剣を置いてきてしまったことを後悔しながら、私は臨戦態勢をとる。たった一人で倒せる相手では
ないことはわかっていたけれど、ここで出会ってしまった以上背を向けて逃げるわけには行かない。
「そうだけど、そんなに怖い顔しないでよ」
構えを取る私を見て、魔王は不愉快そうに眉を寄せて頬を膨らませた。その仕草は、まるで駄々を
こねる幼い子供のようだ。
「ここで君と僕とが戦ったって、どうしようもないじゃない。君はまだまだ弱すぎるからね、すぐ
死んじゃうから面白くない。それよりさ……」
そう言うと魔王は、左手でウオトカの瓶を指差して目を閉じた。その瞬間、空っぽだったはずの瓶
が真っ赤なワインで満たされる。
「僕はウオトカより、こっちの方が好きなんだ。香りが良いからね」
驚きのあまり呆然とその場に立ち尽くす私の手からワインの入った瓶を奪うと、魔王は柔らかな草
の上に座り込んだ。瓶の中からは芳醇なワインの香りが立ち昇り、辺りに流れ出していく。
「一緒に月見酒でも飲もうよ。これも何かの縁なんだから」
ワインを口の中に流し込みながら、魔王は私に笑いかける。その顔にはまったく邪気はなく、ただ
純粋に月見酒を楽しもうとしているように見えた。私はしばらく迷ったが、考えるのも面倒になり魔
王の前に胡坐をかいた。
「はい、君もどうぞ」
差し出されるまま瓶を受け取り、ワインを飲む。甘みの少ない、辛口の味わいが喉に心地よい。
「君は随分酒に強いんだね。ウオトカを一本飲むなんて」
魔王はくすくすと笑いながら、かなりのペースでワインを飲む。もう酔いがまわったのだろう、青
白かった顔には赤みがさしている。
「…あんた、本当に魔王か?」
敵の前でしどけなく酔い、笑みをこぼす目の前の存在が魔王だとは、私にはどうしても思えなかっ
た。どこかの酒場で会った兄ちゃん、そんな感じだ。
「魔王だよ。魔族三万七百四十九種の頂点に君臨し、眷属としてそれらを従える。魔界の誇り高き
王者、デザンディアとは僕のこと。でもね…」
瓶を勢い良く傾け、残り少なくなったワインを飲み干した魔王は、目を細めて月を見上げた。黒色
のローブの袖口が、はたはたと風に揺れている。
「今は、そんな誇りなんていらないと思っているんだ」
空瓶を草の上に置き、魔王はそのまま仰向けに寝転んだ。夜風が気持ちいいのかうっとりと目を閉
じ、深呼吸をしている。
「そんな誇りがいくらあっても、あの人の心は変えられない。僕の孤独も終わらないんだ」
寝転んだままの魔王をじっと見据え、私は立ち上がって鎧を脱ぎ捨てる。鎧のまま寝転がっても、
草の柔らかな感触は味わえない。
「あの人って、リリア姫か?」
鎧を脱ぎ捨て、布の服姿で魔王の隣に寝転がった私は、月を見ながら小声で呟く。魔王さえも魅了
した、美姫の顔を月に重ねながら。
「そう、リリア姫のことだよ。僕はこう見えても紳士だから、レイプしたりはしない。お茶と食事
は欠かさずに供するし、退屈を紛らわすための小さな犬も差し入れたんだ」
目を開けて隣に寝転んだ私の様子をしばらく観察した後、魔王も月を見上げてぽつりぽつりと話し
始めた。その声は、風に揺れる草のように弱弱しい。
「もちろん、手錠や拘束具なんか付けてもいないよ。城の中は自由に歩けるし、監視もいない。だけ
ど、駄目だね。魔王である僕は嫌われて、蔑まれているよ。毎日毎日、窓から見える月に姫は祈るん
だ。『カナーレ様、どうぞご無事で』ってね」
魔王はそう言うと、大きくため息をついた。私はちらりとその横顔を見て、目を閉じた。想い合う
恋人たちの美談は、すばらしいの一言に尽きる。だけど……
「僕が魔族でなければ、人として生まれていればこんな風に連れ去ることはしなかった。正々堂々
求婚して、それで断られても仕方がないこととして諦められたと思う。僕は姫を連れ去る前に、何度
も姫に想いを告げようとした。でも、魔王である僕の言葉なんてリリア姫は聞いちゃくれなかった。
魔族とは口を聞くのも嫌なんだろうね」
長い爪、黒いローブ。そして腐臭交じりの甘い体臭。人知を超えたそれらの要素に、嫌悪感を抱く
姫の気持ちもわからなくはない。だけど、その言葉さえ聞かないというのは、あまりにも傲慢のよう
な気がする。
「いまさら何を言っても、言い訳だけどね。愛したことが悪いんだから」
さわさわとした衣擦れの音がして、魔王が立ち上がる気配がした。私は目を開けるでもなく、その
まま寝転んでいる。
「君こそ、本当に僕を倒そうとしている戦士なの?そんなに無防備に寝転がって」
上から見下ろす魔王の視線を感じて、私は目を開けた。魔王の指先にはウェン爺さんが操る、偉大
なる〈原理〉と同じような力でできた黒い炎が揺らめいている。
「ご覧の通り、今のあたしには戦闘意欲や闘争本能なんか働いてないんだよ」
揺らめく黒い炎を見つめたまま起き上がり、私は魔王のそばに歩み寄る。一歩近づくごとに炎の熱
が身体を焼き、表皮が萎縮する痛みが走る。
「それ以上近づくと、君の肌が燃えるよ」
魔王の忠告を無視して、私は炎に手を伸ばす。強烈な痛みと、肉の焼ける音が辺りに立ち込める。
「ほら…ごらん。あたしは…こんなこともできるのさ…」
黒い炎の向こう側にある魔王の手を握り締め、私は引きつった笑みを浮かべて見せた。体から飛び
出していきそうな意識を必死で繋ぎ止め、魔王を見上げる。
「いつか、いつかあんたを…倒すよ。ウェ…ン爺さんと、カナーレ…と一緒にね。でもその前に、
あんた…に言っておき…たいことがあ…る」
魔王は驚いた顔のまま、目も逸らさずに私の顔を見下ろす。肉体がばらばらに砕けてしまいそうな
痛みに、私が耐えていることが信じられないのだろう。
「愛し…たこと…が悪いんじゃな…い。愛し方が悪かっ…たのさ。た…だそれだけだ…よ」
そう言って魔王の手を離した瞬間、私の意識は体から飛び出した。