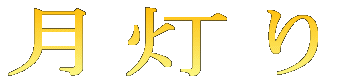
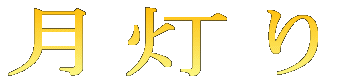
「それじゃあ、あたしはどうしたらいいの?」
腰にぶら下げた剣を置き、私は焚き火の前にドカリと座り込んだ。鉄の鎧ががちゃがちゃと音を立
てる。広々とした草原の、大きな木の根元で。私は眠るカナーレの姿を見ながらそう呟いた。
「諦めることさ。お前さんにはできないことなんだ」
呪力を封じ込めているという杖を持った魔術師のウェン爺さんは私の前に座り、焚き火の火に手を
翳して目を閉じた。私はそんな爺さんの態度が気に入らず、むっとしたまま腕を組む。
「どうして?あたしは……」
「お前さんは、諦めるべきなんだ」
私の言葉を遮り爺さんがそう言ったとき、ぱちりと焚き火の火がはぜた。目の前に赤々と燃える火
があるのに、私の身体は冷え切ったままだ。少しでも暖かくなればと、私は熊の毛皮で身体を包み、
瓶の酒をあおった。
「お姫様ならシルクやビロード、サテンのドレスに身を包む。酒を飲むときだって、華奢なゴブレ
ットに注いでもらったワインなんかを飲むもんさ。それなのにお前さんと来たら……」
最後に立ち寄った街で買ったタバコに火をつけ、爺さんはほうと煙を吐き出した。青白い煙が、エ
クトプラズムのように空に立ち昇ってゆく。
「自分で剥がした熊の毛皮を着て、薄めもしないウオトカを瓶のまま飲む。姫どころか野蛮人その
ものだ」
爺さんの嘆きを黙ってゴハイチョウしていた私だったが、やがて堪えきれずに盛大にウオトカを噴
き出してしまった。
「それは当たり前だろう、爺さん。あたしは戦士だ、お姫さんじゃない」
鎧の胸元にあるエンブレムをさすり、私は胸を張る。私やカナーレの生まれた国では、十二歳にな
った時から才能ある一部の人間に英才教育が施される。その内容は医術や語学、史学などといった一
般的なものから、魔術や戦術・剣術など物騒なものまで様々だ。そしてその英才教育を無事に終えた
ものは国の要人として尊敬され、国の発展に尽くすという仕組みになっている。
ここですっかり耄碌したようにタバコをふかすウェン爺さんも、魔術や呪術のエキスパートとして
の英才教育を受けた一人だ。私なんかじゃ百年かかってもわからない〈原理〉とやらを操り、火をお
こしたり地面に穴を開けたり、とんでもないことをしでかしてくれる。
「このエンブレムが、あたしの誇りさ。体術、剣術。そして、あらゆる武術を修めたものに与えら
れる、戦士のエンブレム。あたしは誇り高い戦士なんだ」
戦士たるもの世界に存在するありとあらゆる武術を継承し、己の技に驕ることなく研鑽を積むこと
を誇りとすべし。戦士団の団長を勤める叔父が、エンブレムの贈呈式で私にそう言ってくれた。女の
戦士は数が少なくて珍しかったからか、式では国王陛下にまで握手を求められて照れくさかった。だ
から、このエンブレムこそが私の誇りだ。
「お前さんは、カナーレにとっては便利な道具なんだよ」
ウェン爺さんは短くなったタバコを焚き火の中に放り込み、ゆらゆらと動く火をじっと見つめる。
その顔は、老人特有の険しさを帯びていた。
「お前さんは、カナーレの欲望のための剣に過ぎん。望むものを手に入れたとき、お前さんのこと
など忘れ去られる……」
「回りくどいこと言ってないで、はっきり言ったらどうなんだい」
ビン底のウオトカを一息で飲み干し、私は爺さんを睨み付けた。爺さんの言いたいことはわかって
いたけれど、自分の口から言うのは癪だった。
「リリア姫が無事に救出されたとき、お前さんのことなどカナーレは忘れるんだ。だから諦めろと
言いたいんじゃ」
爺さんが口にしたリリア姫という名前に、私の心がざわついた。華奢な肢体と、可憐な美貌。こ
世に神が遣わしたもうた天使だと、国民が口を揃えて賛美する王の一人娘。そしてその美ゆえに魔に
魅入られ、今では魔王に捕らわれている悲劇の王女、リリア姫。
もちろん私も、彼女の美しさと心優しさには尊敬と敬愛を抱いている。だからこそリリア姫奪還の
命を受けたときは、国民の期待を重く受け止め勇んで国を後にした。だけど……。
「あたしは、愛されたいんじゃない。ただ愛しているだけさ」
眠るカナーレに視線を投げると、私の心はどんよりと重く沈む。カナーレはリリア姫の婚約者で、
貴族の息子だ。何の力もないくせに姫を救うと城を飛び出した、身の程知らずのぼんぼん。そんなカ
ナーレの面倒を、私とウェン爺さんはここまで見てきた。
「それ以上を望みはしないよ」
今でこそ若干の治癒能力と剣術を身につけて、魔王の配下とも渡り合えるようになってきたけれど
。旅の始めの頃なんか、カナーレは話にならないような腰抜けだったのだ。ただ、それでも前に進ん
でいこうとするその意思の強さを見ているうちに、私はいつの間にかカナーレに惚れていた。
カナーレの優しさも強さも、綺麗な横顔も戦いでついた傷も。みんなみんなリリア姫のものだとい
うことくらい、脳味噌まで筋肉といわれる私でも理解している。理解しているが、時々わからなくな
る。
「だから受け入れるのか?カナーレの傲慢さを」
「知ってたのか、爺さん……」
私は空になったウオトカのビンを脇に置くと、湧き上がってきた羞恥心を隠すために顔を伏せた。
目を閉じても、炎の赤さのせいで闇の中には潜れない。
私とカナーレは、何度かセックスをしている。もちろん、私から誘ったわけじゃない。カナーレが
寝ていた私を強姦したのが、この関係の始まりだった。
『眠れないんだ……』
そんな言葉を口にしながら、やけに手馴れた動作で私の服を脱がしたその時のカナーレの顔を、私
は今でも鮮明に覚えている。突き飛ばすとか、切り付けるとかすれば良かったのかもしれない。だけ
どカナーレの目を見た私は、何も言えずにただ受け入れてしまった。
街で街娼を買うより安価で、歩く女に声をかけるより安全。私相手ならば、そんな風にお手軽に自
分の欲望を満たせると思ったのだろう。柔らかな腕や、滑らかな肌がないことにさえ目をつぶれば。
「知りたくなんかなかったがな。カナーレのリリア姫への裏切りも、お前さんの涙も」
ウェン爺さんの低い声音に促されるように顔を上げると、爺さんはカナーレの背に視線を当てたま
まで二本目のタバコに火をつけるところだった。偉大なる〈原理〉を指先から出る炎に変え、咥えた
ままのタバコに近づけている。
「あたしは泣いてなんかないよ。処女じゃあるまいし、減るもんでもないしね」
豆やひび割れでがさつく手に視線を落とし、私はため息をついた。偉大なる〈原理〉を操ることも
、たおやかな仕種もできない自分の手を、私は恨めしく思う。熊を一撃で仕留められ、レンガの壁を
破壊することのできる手。それを誇りに思えたのは、旅に出る前までのことだ。
セックスの度にカナーレは私の手に触れ、はっとした顔ですぐ手を離す。リリア姫の柔らかでか細
い手とは、あまりにも違いすぎるからだろう。そんなことが繰り返されるたびに、私はこの手が誇れ
なくなり、今では嫌悪さえ抱くようになったのだ。
「わしのような、棺桶に半分足を突っ込んだ年寄りが言うことではないかもしれんが。お前さんは
十分女としての魅力を備えている。わしが後二十歳も若ければ、赤い薔薇を差し出して求婚したいく
らいさ」
爺さんは指先の炎を薔薇の形に変え、ぽんと空気中に浮かべた。薔薇はすぐに燃え尽きて、闇の中
に消えていく。
「だから、そんなお前さんが悲しむのは見たくない」
「……あたしにそんなことを言うのは、爺さんくらいのもんだよ」
優しい爺さんの言葉に苦笑いを返し、私はウオトカの空瓶を持って立ち上がった。その時、焚き火
の向こう側で寝ていたカナーレが、ごろりと寝返りを打ってこちらを向いた。目覚めた気配はなく、
月灯りと同じ金色の髪が微風に揺れている。
「少し、風に当たってくるよ。先に寝ててくれ」
大きく輝く月に誘われるように、私は草原の中を歩き出す。あたりの草は夜風になぶられ、絶えず
ざわざわと音を立てていた。