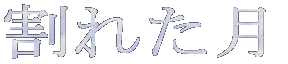
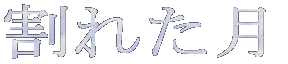
「ほら、兄さん女好きだったからさ。ついに地上の女じゃ飽き足らなくなって、人魚姫か乙姫様を探しに
行ったんだよ」
「……」
私が笑いながらそう言っても、隣に立っている近藤さんは笑わなかった。ただ黙って、暗い水面に浮かぶ
月に視線を向けている。波が打ち寄せる海岸は静かに、夜空の月を写していた。
「みつかったらさ、あのお得意の口説き文句を連発するんだろうね。でも人魚姫とか乙姫様に、日本語っ
て通じるのかな」
何の言葉も返ってこないのに、私はさらに言葉を紡ぎ続けた。何かを口にしていないと、気が狂いそう
だ。夜の海に揺れる月には、そんな魔魅がある。気を抜くとこの中に引きずり込まれてしまうような気が
するほどに。
「どれだけ兄さんが口説いても言葉が通じなかったら、意味ないのにね。それに……」
「もう、黙ってろ」
近藤さんはそう言うと、私の口を大きな手でふさいだ。その手の中で私はそろそろと口を閉じ、近藤さ
んを見上げた。水面の月に向けられていた視線が私に注がれた時、私の視界はぼやけ始めた。
「黙って、泣け」
口をふさいでいた手を離すと、近藤さんは私の肩をそっと抱いてくれた。私の目の奥で凍り付いていた
涙が、近藤さんの手の温かさで解けて溢れ出す。涙は地面を叩き、私に悲しみを自覚させる。認めたくは
なかったのに。
昨日この海で。私にとっては兄であり、近藤にとっては友人だった男。坂田英輔が月を割って死んだ。
***********************************************
「兄さん……」
「お前がそんな顔しなくてもいいんだよ」
がらんとしたオフィスに行くと青白い顔のまま、兄さんは私に笑いかけてくれた。たくさんの恋人がい
て、いつだって華やかに笑っていた兄さんの面影はもうそこにはない。苦しみという薄氷の上に作られた
微笑は痛々しいだけだ。
「全ては、俺のしたことなんだから」
兄さんはそう言って、痛々しい微笑を浮かべ続ける。兄さんにこんな顔をさせているのは、とんでもな
い額の借金だ。兄さんと一緒に小さな会社を経営していた恋人の猪瀬さんが、兄さんを連帯保証人にして
借金をしていたのだ。もちろん兄さんはそんなことを知らなくて、気付いたときには猪瀬さんは借金を残
して消えていた。
「英輔」
私と兄さんが暗い気持ちで向き合っていると、背後から低く柔らかな声がした。振り返ると兄さん昔か
らの友人で、私とも旧知の仲の近藤修一さんが立っていた。その顔はやっぱりどこか疲れきっていて、兄
さんを取り巻く環境の悲惨さが滲んでいる。
「どうした?」
近藤さんが手近にある椅子に腰掛けるのを待って、兄さんは愛飲している黒い箱に入った煙草を取り出
した。火をつけられた煙草の先端が赤く燃えるのを、私はぼんやりと眺めていた。
「本気なのか?昨日の話」
「あぁ、あれか。本気だよ、この会社はお前に頼むつもりだ」
近藤さんは困惑した表情を隠せないまま、同じ煙草を自分のスーツの中から取り出して火をつける。私
はまた赤く燃える煙草の先端を見ながら、立ち上がった。ややこしい話の中に部外者が立ち入るのは、あ
まりいいことではないだろうと思って。
「淳、まだ座ってろ」
立ち上がった私に、兄さんは鋭い視線を向けてきた。いつもの穏やかさが消えてしまったような兄さん
の様子に困惑したまま、私はもう一度椅子に座りなおす。兄さんが何か大切なことを言おうとしていると
いうことだけは、困惑した私の頭でも理解できた。
「この会社は小さいけれど、業績は悪くない。それは営業をやってくれている修一のお陰だ。それにこの
会社を畳むことは、他の従業員に迷惑をかけることにもなる。借金は俺の個人的な問題だから、俺が退陣
すれば問題はないだろう」
白い煙を吸い込んで吐き出しながら、兄さんは近藤さんに静かに語りかける。近藤さんは口をはさむこ
となく、黙って兄さんの話を聞いている。兄さんはこの会社を愛していたんだと、私は改めて実感した。
「……わかった。英輔が望むなら、そうしよう」
しばらく沈黙した後、近藤さんは携帯灰皿にタバコを押し込みながら小さな声で呟いた。その言葉を聞
いた兄さんの顔に、安堵の表情が浮かぶ。
「ただし、預かるだけだからな。さっさと借金返して戻って来いよ」
唇の端を持ち上げて笑い、近藤さんは立ち上がった。兄さんは少しだけ驚いたように目を見開いた後、
黙って目を伏せる。近藤さんの優しさに兄さんより私のほうが感動してしまって、滲んできた涙をハンカ
チでごしごしと拭いた。
「お前、目が真っ黒だぞ」
「本当だ。淳、顔洗って来いよ」
近藤さんが私の顔を見て吹き出すと、兄さんも私の顔を覗き込んで笑う。さっき涙を拭いたハンカチを
見てみると、マスカラが落ちたらしい黒いシミができていた。
「うん」
椅子を蹴って立ち上がると、私はトイレに駆け込んだ。真っ黒になっている目を拭きながら、私はまた
少しだけ涙を零した。こんな風に笑いあえる日常が、またすぐに戻ってくることを願いながら。
***********************************************
だけど、その夜。兄さんはここから見えるあの崖から、月の浮かぶ水面に身を投げた。遺書はなかった
けれど、多額の生命保険を自分自身にかけていたことから借金を苦にしての自殺だと警察は断定した。
「英輔は、猪瀬に裏切られたことのほうがショックだったんだろうな」
泣いて、泣いて。私が少しだけ平静を取り戻すと、近藤さんはぽつりぽつりと兄さんと猪瀬さんの関係
を私に教えてくれた。
「英輔は猪瀬以外の女とは、みんな別れて。猪瀬と結婚するつもりだったんだ。猪瀬が英輔をどう思って
いたかはわからないけどな」
近藤さんの話を聞いていると、水面の月の上に猪瀬さんの綺麗な横顔が浮かんだ。いつだって凛として
いた綺麗な猪瀬さんは、兄さんを愛していたのだろうか。兄さんが死んだことを知ったら、涙を流してく
れるのだろうか。揺れる横顔に問いかけてみても、答えは返ってこない。
「兄さんは……兄さんは……」
私はうわごとのように呟くと、ふらふらと服のまま海の中に入っていく。まだ泳ぐには冷たい海水が、
私を包んで取り込んでいく。海の底に残っているはずの、兄さんのカケラを探すために。
「待てっ」
近藤さんの制止を振り切り、私は海の中を進んだ。胸元まで水につかった私は、水面に浮かぶ月を手の
ひらに掬い上げた。揺れる水の中に目を凝らしてみても、兄さんの姿はない。どれだけ掬い上げても、月
はいつまでも水面に浮かんでいる。兄さんは消えてしまったのに、月は相変わらず明るいままだ。私はも
う一歩、海の底に向かって足を踏み出そうとした。
「待てっていったら素直に待て!」
その時、そんな言葉と共に近藤さんが私の体を強く引いた。バランスを崩した私は、近藤さんの腕の中
に倒れこむ。海水に体温を奪われていたせいか、近藤さんの体はとても温かかった。
「お前まで、俺を置いていくな」
耳元で囁かれた近藤さんの声が、細かく震えている。悲しいのは、私だけじゃない。近藤さんだって、
兄さんの死をまだ受け止め切れていないのだろう。
「置いていかないでくれ」
震える近藤さんの言葉に、私は無言で頷く。私を抱いてくれている手に、自分の手を重ねた後。私は両
手を大きく振り上げて、水面の月を叩き割る。月の灯りに照らされた水しぶきは私の顔や髪を濡らした後
、また再び海に還っていった―。
昨日この海で。私にとっては兄であり、近藤にとっては友人だった男。坂田英輔が月を割って死んだ。
そして今日、この海で。私は同じように月を割って悲しみを殺した。生きていくために。日常の中に還
っていく、そのために。
Fine.